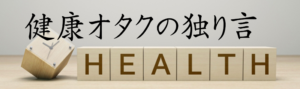「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」――そんな睡眠トラブルに悩まされていませんか?
実は、寝る前に無意識で行っている“ちょっとした習慣”が、質の良い睡眠を妨げている可能性があります。この記事では、睡眠の質を下げる5つのNG習慣と、その改善方法を詳しく解説します。
目次
寝る前のNG習慣1:スマホ・パソコンの長時間使用
ブルーライトが睡眠ホルモンを妨げる
スマートフォンやパソコン、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」には、脳を覚醒させる作用があります。ブルーライトはメラトニンという睡眠ホルモンの分泌を抑え、体内時計を乱すため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなる原因になります。
対策:寝る1時間前にはデジタルデトックスを
就寝前1時間はスマホやPCの使用を控える「デジタルデトックス」がおすすめです。どうしても使用が避けられない場合は、ブルーライトカット眼鏡の着用や、画面の「夜間モード」を活用するとよいでしょう。
寝る前のNG習慣2:カフェインの摂取
コーヒーやお茶が眠気を遠ざける
カフェインは脳を覚醒させる作用があり、摂取後4〜6時間はその効果が持続します。就寝前にコーヒーや緑茶、エナジードリンクなどを飲むと、なかなか寝付けなかったり、睡眠の質が低下する原因になります。
対策:夕方以降のカフェインは控えよう
午後3時以降はカフェインを控えるのが理想です。夜に温かい飲み物を飲みたくなったときは、カフェインレスのハーブティー(カモミールやラベンダーなど)がおすすめです。
寝る前のNG習慣3:激しい運動
高まった体温が入眠を妨げる
筋トレやランニングなどの激しい運動を寝る直前に行うと、体温や心拍数が上がり、脳が興奮状態になってしまいます。入眠には体温が徐々に下がっていくことが必要であるため、逆効果になることがあります。
対策:運動は就寝2~3時間前までに
適度な運動は睡眠の質を高めますが、タイミングが重要です。ウォーキングやヨガなどの軽めの運動を夕方に取り入れ、寝る前は深呼吸やストレッチでリラックスするのが効果的です。
寝る前のNG習慣4:アルコールの摂取
一時的な眠気と引き換えに睡眠の質が低下
お酒を飲むと「すぐ眠くなるから良いのでは?」と思われがちですが、実は逆効果。アルコールは浅い眠り(レム睡眠)を減らし、夜中に何度も目が覚める原因になります。さらに、利尿作用によって夜間のトイレも増え、睡眠を妨げてしまいます。
対策:就寝3時間前までに済ませよう
お酒を楽しみたい場合は、できるだけ就寝の3時間前までに飲み終えるのが理想です。また、飲酒後は水をしっかりと摂って、アルコールの分解を助けるようにしましょう。
寝る前のNG習慣5:考えごと・悩み事
頭が冴えて寝付けなくなる
仕事の不安や人間関係の悩みなど、寝る前にあれこれ考えてしまう人は多いでしょう。ですが、こうした思考は脳を活性化させてしまい、寝付けなかったり、眠りが浅くなる原因になります。
対策:頭を「休ませる時間」を意識的に作る
寝る前はスマホやSNSを見ず、ゆったりとした音楽や読書、深呼吸などで脳をリラックスさせる時間を取りましょう。また、思考を整理したいときは、紙に書き出して“頭の外”に出すことで、不安やモヤモヤを軽減する効果もあります。
睡眠の質を高めるためのプラス習慣
毎日同じ時間に寝て起きる
体内時計を整えるには、毎日の就寝・起床時間をなるべく固定することが大切です。休日も平日との差を1時間以内にすることで、リズムが乱れにくくなります。
寝室の環境を整える
快適な睡眠には、温度・湿度・光・音の環境も重要です。部屋はやや暗めで静かに、温度は夏は25〜26℃、冬は20〜22℃程度が理想です。また、遮光カーテンや加湿器を活用すると、より深い眠りに入りやすくなります。
まとめ:寝る前の習慣を見直して、質の高い睡眠を手に入れよう
睡眠の質を下げる原因は、実は日常のちょっとした習慣に潜んでいます。スマホの使用やカフェイン、運動・飲酒・考え事など、知らず知らずのうちに眠りを妨げている行動は多くあります。
この記事で紹介した5つのNG習慣を見直し、自分に合ったリラックス法や就寝準備を取り入れることで、ぐっすり眠れる毎日を取り戻しましょう。睡眠が整えば、心も体も軽くなり、日中のパフォーマンスも自然と高まっていきます。