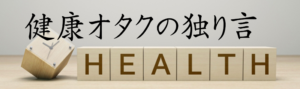「健康のために栄養を意識しているのに、なぜか体調が良くならない…」
もしかすると、それは“食べ合わせ”が原因かもしれません。
実は、どんなに栄養価の高い食材を選んでも、組み合わせ次第で吸収が妨げられたり、逆に体に負担をかけることもあるのです。
この記事では、意外と知られていない「体に悪い食べ合わせ5選」と、栄養をしっかり活かすための正しい食事法について解説します。
目次
食べ合わせが体に与える影響とは?
栄養の吸収効率に大きく関わる
食材同士の相性によって、栄養素の吸収率が高まる場合もあれば、逆に吸収を妨げてしまうこともあります。たとえば、鉄分とビタミンCを一緒に摂ると吸収が促進されますが、カルシウムと鉄分を一緒に摂ると吸収を妨げてしまうことがあるのです。
消化器官への負担にも影響
ある食材の組み合わせは、胃腸に負担をかける原因にもなります。結果として消化不良や胃もたれ、栄養の未吸収が起きることもあるため、注意が必要です。
体に悪い食べ合わせ1:トマト×きゅうり
ビタミンCが分解されてしまう!
トマトはビタミンCが豊富な食材ですが、きゅうりには「アスコルビナーゼ」という酵素が含まれており、これがビタミンCを分解してしまいます。
せっかくの栄養がムダになってしまう典型的な食べ合わせです。
対策:酢やレモン汁で酵素を抑える
アスコルビナーゼは酸に弱い性質があるため、酢やレモン汁で和えることで分解を抑えることができます。トマトときゅうりを一緒に食べるときは、酸味のあるドレッシングを使うのがおすすめです。
体に悪い食べ合わせ2:納豆×卵
ビオチンの吸収が阻害される
納豆と卵の組み合わせは朝食の定番ですが、生卵の卵白に含まれる「アビジン」という成分が、ビタミンB群の一種「ビオチン」と結合して吸収を妨げてしまいます。
対策:卵は加熱してから使おう
アビジンは加熱によって不活性化するため、納豆に卵を加える場合は「温泉卵」や「炒り卵」など火を通したものを選ぶと、ビオチンの吸収を妨げずに済みます。
体に悪い食べ合わせ3:カフェイン×鉄分
鉄分の吸収が大きく阻害される
カフェインはコーヒーや緑茶に多く含まれていますが、これらは鉄分の吸収を妨げる働きがあります。特に女性や貧血気味の方には注意が必要な組み合わせです。
対策:カフェインは食後1〜2時間空けて
鉄分を多く含む食事を摂る際は、カフェインの摂取タイミングをずらしましょう。どうしても飲みたい場合は、ノンカフェインの麦茶やルイボスティーを選ぶのも一つの方法です。
体に悪い食べ合わせ4:天ぷら×スイカ
胃腸に大きな負担をかける
油っこい天ぷらと水分量の多いスイカを同時に摂ると、胃腸が冷えやすくなり、消化不良や下痢を引き起こすことがあります。特に胃腸の弱い人や冷え性の方は避けた方が無難です。
対策:スイカは食後30分以上空けて
スイカなどの水分を多く含む果物は、油ものを食べた後は時間を空けてから摂取するのが理想です。お腹の調子を崩さず、両方の美味しさをしっかり楽しむことができます。
体に悪い食べ合わせ5:チーズ×白ワイン
カルシウムと酸がぶつかり合う?
チーズに含まれるカルシウムと、白ワインに含まれるシュウ酸や酒石酸が反応すると、不溶性の塩ができてしまい、カルシウムの吸収を妨げるといわれています。
対策:赤ワインや水と合わせて楽しむ
チーズをお酒と楽しみたい場合は、シュウ酸の少ない赤ワインや、合間に水を飲むことでバランスがとりやすくなります。カルシウムの吸収も妨げにくくなります。
栄養をムダにしないための食事のコツ
食材の相性を知って組み合わせる
「トマト×ブロッコリー」「鉄分×ビタミンC」「カルシウム×ビタミンD」など、栄養素の吸収を高める組み合わせを意識することで、より健康的な食事に近づけます。
よく噛んでゆっくり食べる
食べ合わせも大切ですが、基本となるのは「よく噛むこと」。唾液の分泌が促されて消化がスムーズになり、胃腸への負担も軽減されます。
まとめ:知って得する!食べ合わせの知識で体に優しい食事を
体に良いと思って食べていたものでも、組み合わせによっては栄養をムダにしていたり、逆効果になっている可能性があります。
この記事で紹介したような「避けたい食べ合わせ5選」と「改善方法」を意識することで、毎日の食事の質をぐっと高めることができます。
大切なのは、知識を取り入れて柔軟に応用することです。賢い食べ合わせで、より健康的な食生活を目指しましょう!