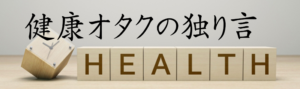私たちが毎日口にする食品には、保存料や着色料、甘味料などの食品添加物や、農薬・包装材などに含まれる化学物質が多く含まれています。
安全性が確保されているとはいえ、長期間にわたり摂取し続けた場合の健康への影響を不安視する声も少なくありません。
この記事では、食品添加物や化学物質が健康に与えるリスクと、なるべく摂取を減らすための工夫について、わかりやすく解説します。
目次
食品添加物と化学物質の違いとは?
食品添加物とは?
食品添加物とは、食品の製造・加工・保存のために使われる物質で、日本では約1500種類が認可されています。主に以下のような目的で使用されています。
- 保存性を高める(防腐剤・酸化防止剤)
- 見た目を良くする(着色料・光沢剤)
- 味を調える(甘味料・調味料)
- 食感を改善する(増粘剤・ゲル化剤)
化学物質とは?
ここでいう化学物質とは、農薬、プラスチック包装材、洗剤、合成香料など、日常生活で無意識に接している化学成分全般を指します。
食品だけでなく、住環境や日用品を通じて体内に取り込まれることもあります。
添加物・化学物質が健康に与える主なリスク
1. アレルギーやアトピーの悪化
一部の添加物(保存料、着色料など)は、アレルギー反応を引き起こしたり、アトピー性皮膚炎を悪化させる可能性があるとされています。特に小さな子どもは免疫機能が未発達なため注意が必要です。
2. 腸内環境の乱れ
食品添加物の中には、腸内細菌のバランスを崩すとされる成分もあります。腸内環境が乱れると、免疫力の低下・肌荒れ・便秘・精神的な不調など、さまざまな不調につながる可能性があります。
3. 内分泌かく乱作用(環境ホルモン)
ビスフェノールA(BPA)やフタル酸エステル類など、プラスチック容器に含まれる化学物質は、体内でホルモンのように作用し、内分泌バランスを乱す(いわゆる環境ホルモン)といわれています。
4. 発がん性の懸念
一部の人工甘味料や合成着色料などには、長期的な摂取により発がん性が疑われている成分もあります。日本で使用が認可されている添加物でも、海外では禁止されているものも存在します。
添加物や化学物質の摂取を減らすためにできること
加工食品の「裏表示」をチェックする
お弁当・総菜・冷凍食品・お菓子などには、多くの添加物が使われていることがあります。購入前には食品表示ラベルを確認し、なるべく添加物の少ない商品を選ぶようにしましょう。
避けたい主な添加物の例
- アスパルテーム(人工甘味料)
- タール系着色料(赤◯号、黄◯号など)
- グルタミン酸ナトリウム(うま味調味料)
自炊を習慣にする
外食やコンビニ食は便利ですが、添加物が多く含まれやすい傾向があります。自炊することで、使用する食材や調味料を自分でコントロールできるため、無添加・低添加の食生活に近づけます。
保存容器の素材に気をつける
プラスチック製の食品容器は、電子レンジ加熱時に有害物質が溶け出す可能性があります。できればガラス製や陶器製の容器に切り替えるのがおすすめです。
オーガニック食品や無添加製品を選ぶ
すべてを無添加にするのは難しくても、「調味料だけは無添加にする」「おやつはオーガニックを選ぶ」など、無理なくできる範囲から始めることが継続のコツです。
添加物=すべて悪ではない。正しい知識も重要
添加物には安全基準がある
日本で使用が認められている食品添加物は、厚生労働省の安全審査をクリアしたものに限られています。少量であれば健康に影響が出ないような使用量が設定されています。
過剰な不安より“知って選ぶ”が大切
すべての添加物を避けるのは現実的ではありませんし、過剰な不安やストレスは逆に健康に悪影響です。
大切なのは、**「どんな成分が使われているかを知り、自分で選ぶ意識を持つこと」**です。
まとめ:体を守るために“少しの意識”から始めよう
食品添加物や化学物質は、現代の生活に欠かせない一方で、過剰な摂取や長期間の蓄積によって健康リスクを高める可能性があります。
毎日の中でできることから、少しずつ取り入れていきましょう。
- 添加物の表示を確認する習慣をつける
- 自炊や無添加調味料を取り入れる
- 容器や包装材の素材を見直す
- 情報に振り回されず、自分で選ぶ力を持つ
こうした“ちょっとした意識”の積み重ねが、将来の健康を守る力になります。まずは今日の買い物から、意識を変えてみませんか?