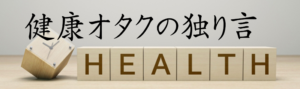「カロリーは気にしているけど、食物繊維はあまり意識していない」――そんな人は意外と多いのではないでしょうか。実は、健康を保つうえでカロリー制限以上に大切とも言われるのが「食物繊維」です。
近年では、高齢者を中心に便秘や血糖値、コレステロールなどの問題を抱える人が増えており、食物繊維の重要性があらためて注目されています。本記事では、食物繊維の基本的な役割から、具体的な健康効果、摂取のコツまでをわかりやすく解説します。
目次
食物繊維とは?2種類の働きを知ろう
食物繊維は、人の消化酵素では分解されない「第6の栄養素」として知られており、大きく2種類に分けられます。
不溶性食物繊維
水に溶けず、水分を吸収して膨らむ性質があります。便のかさを増やして腸を刺激し、排便を促す働きがあります。
主な食材:野菜(ごぼう、キャベツ)、豆類、穀物、きのこ類
水溶性食物繊維
水に溶けてゲル状になり、腸内での糖や脂質の吸収をゆるやかにします。腸内の善玉菌を増やす「プレバイオティクス」としても注目されています。
主な食材:海藻類、果物(りんご、バナナ)、大麦、納豆
食物繊維が健康にもたらす5つのメリット
1. 便秘の改善・予防
高齢者に多い便秘は、腸のぜん動運動の低下や食事量の減少が原因です。食物繊維をしっかり摂ることで、便の量と柔らかさが保たれ、自然な排便が促されます。
2. 腸内環境の改善
水溶性食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内フローラ(腸内細菌バランス)を整える役割があります。腸内環境が整えば、免疫力向上やアレルギー予防にもつながります。
3. 血糖値の上昇を抑える
食物繊維は糖質の吸収を遅らせるため、食後の急激な血糖値上昇を抑えます。糖尿病予防・改善にも効果的で、GI値(血糖値の上昇度)を下げる働きがあります。
4. コレステロールの低下
水溶性食物繊維は、腸内でコレステロールの再吸収を抑える働きがあり、悪玉(LDL)コレステロールの低下が期待できます。動脈硬化や心疾患の予防にも効果があります。
5. 食べすぎ防止・ダイエット効果
食物繊維は消化に時間がかかるため、満腹感が持続しやすくなります。食べすぎを防ぐだけでなく、脂質や糖の吸収を抑えることで、体脂肪の蓄積も予防できます。
食物繊維の目標摂取量と現状
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日あたりの食物繊維摂取目標量は以下のとおりです。
- 男性(65〜74歳):20g以上
- 女性(65〜74歳):17g以上
しかし実際の摂取量は、多くの人が1日約12g前後にとどまっており、目標に届いていないのが現状です。
食物繊維を効果的に摂るコツ
毎食に野菜を1皿以上取り入れる
副菜として野菜炒め、煮物、サラダを毎食に加えることで、自然と食物繊維の摂取量が増えます。緑黄色野菜や根菜を意識すると◎
主食は「白米」から「玄米・もち麦」へ
白米よりも玄米やもち麦、雑穀米のほうが食物繊維が多く含まれています。白米に混ぜるだけでも効果的です。
おやつは果物・ナッツ・寒天などを活用
クッキーやスナック菓子の代わりに、バナナやりんご、無塩ナッツ、寒天ゼリーなど、自然な食物繊維が含まれるおやつを選びましょう。
発酵食品と組み合わせて腸活効果アップ
ヨーグルト、納豆、味噌汁などと一緒に食物繊維を摂ると、腸内細菌のバランスがより良好になります。
まとめ:カロリー制限より「食物繊維」が健康を左右する
カロリーばかりを気にして食事量を減らすと、かえって便秘や代謝低下、栄養不足を招くことがあります。それよりも、「食物繊維をしっかり摂ること」が、健康的な体作りの土台になります。
毎日の食事に野菜・海藻・穀物・発酵食品を取り入れ、自然と腸内環境を整えながら、病気になりにくい体を目指しましょう。